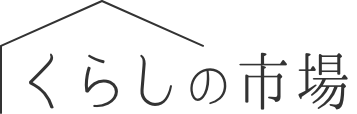窓ガラスの汚れに悩んでいるあなたへ。 じつは、アルカリ電解水をつかうだけで、驚くほど簡単に窓がピカピカになることをご存知でしょうか。
プロの清掃業者もつかっている「アルカリ電解水」は、窓掃除の常識をくつがえす画期的なアイテムです。 二度拭きいらずで、手垢や油汚れもスッキリ落とせる優れもの。 しかも、化学物質をつかわないから、お子さまやペットがいるご家庭でも安心してつかえます。
この記事では、アルカリ電解水をつかった窓掃除の方法を、初心者でもわかりやすく解説します。 基本の掃除手順から、網戸やサッシの掃除方法、さらには車の窓掃除まで、幅広くカバー。 読み終わるころには、あなたも窓掃除のプロになれるはずです。
目次
アルカリ電解水が窓掃除に効果的な理由

窓ガラスの汚れの正体とアルカリ電解水の相性
窓ガラスについている汚れは、じつは内側と外側でまったく違うということをご存知でしょうか。 家の内側についている汚れの正体は、主に「手垢」「ホコリ」「油汚れ」「タバコのヤニ」などです。 これらの汚れは、ほとんどが「酸性」または「タンパク質」でできています。
一方、外側の汚れは「雨水」「砂」「泥」「黄砂」「花粉」「排気ガス」などが中心です。 これらの汚れは、日光によって固着し、汚れ同士が結びついて落ちにくくなるという特徴があります。 とくに、車の交通量が多い道路に面している窓は、排気ガスによる黒い汚れが目立ちます。
アルカリ電解水が窓掃除に効果的な理由は、これらの「酸性汚れ」を中和して分解する力があるからです。 マイナスイオン成分が、物体と汚れのスキマに入り込み、汚れを浮かせて落とします。 この浸透力の高さが、アルカリ電解水の最大の強みなのです。
窓の内側の汚れに対するアルカリ電解水の効果:
• 手垢、皮脂汚れ → 強力に分解
• 油汚れ(調理中の油煙など) → すばやく乳化して除去
• タバコのヤニ → 黄ばみまでスッキリ
• 食べこぼし、飲みこぼし → 簡単に拭き取り可能
• よだれ(赤ちゃんやペット) → 安全に除去
pH値と洗浄力の関係
アルカリ電解水の洗浄力は、「pH値」によって大きく変わります。 pH値とは、液体の酸性・アルカリ性の強さを表す数値で、0から14までの範囲で示されます。 中性がpH7で、それより高い数値がアルカリ性、低い数値が酸性です。
窓掃除に適したアルカリ電解水のpH値は、最低でも「pH11以上」が必要です。 pH11以上になると「強アルカリ性」と呼ばれ、頑固な汚れも落とせる洗浄力を発揮します。 さらに、pH12.5以上のアルカリ電解水には、除菌・消臭効果もプラスされます。
| pH値 | 分類 | 洗浄力 | 窓掃除への適性 |
|---|---|---|---|
| pH8~11 | 弱アルカリ性 | 軽い汚れのみ | △ |
| pH11~12 | 強アルカリ性 | 油汚れも落とせる | 〇 |
| pH12.5以上 | 強アルカリ性 | 除菌効果もあり | ◎ |
ただし、pH値が高すぎると、手荒れのリスクや素材へのダメージも考えられます。 家庭での窓掃除には、pH12~13程度のアルカリ電解水がもっともバランスがよいでしょう。 この範囲なら、高い洗浄力と安全性を両立できます。
二度拭き不要!アルカリ電解水のメリット

従来の窓掃除では、洗剤で汚れを落としたあと、水拭きで洗剤を落とす「二度拭き」が必要でした。 しかし、アルカリ電解水なら、この面倒な二度拭きが不要になります。 なぜなら、アルカリ電解水の主成分は「水」だからです。
アルカリ電解水をつかった窓掃除の最大のメリットは、その「手軽さ」にあります。 スプレーして拭くだけで、汚れが落ちて、そのまま乾かせばピカピカの仕上がりに。 界面活性剤をつかっていないので、拭き跡も残りません。
アルカリ電解水の主なメリット:
• 二度拭き不要で時短になる
• 界面活性剤不使用で環境にやさしい
• 化学物質を含まないので安全
• 除菌・消臭効果もある(pH12.5以上)
• 1本で家中の掃除に使える • コストパフォーマンスが高い
また、アルカリ電解水は「揮発性」が高いという特徴もあります。 拭いたあとすぐに水分が蒸発するので、水滴の跡が残りにくいのです。 これは、窓掃除において非常に重要なポイントです。
窓掃除に必要な道具と準備

基本の掃除道具リスト
アルカリ電解水をつかった窓掃除を始める前に、必要な道具をそろえましょう。 じつは、窓掃除に必要な道具は意外と少なく、すべてそろえても5,000円程度で済みます。 一度そろえれば長くつかえるので、初期投資としては決して高くありません。
基本の掃除道具リスト:
- アルカリ電解水(pH11以上のもの)
- スクイージー(水切り用)
- マイクロファイバークロス(2~3枚)
- タオルまたは雑巾(2~3枚)
- ゴム手袋(肌が弱い方用)
- バケツ(すすぎ用)
- 脚立(高い窓用)
これらの道具があれば、プロ並みの窓掃除ができます。 とくに重要なのが「アルカリ電解水」「スクイージー」「マイクロファイバークロス」の3つ。 この3つがあれば、8割がた窓掃除は成功したようなものです。
| 道具 | 用途 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| アルカリ電解水 | 汚れ落とし | pH11以上を選ぶ |
| スクイージー | 水切り | 幅30cm程度が使いやすい |
| マイクロファイバークロス | 仕上げ拭き | 毛足が短めのものを |
| タオル | 水拭き用 | 使い古しでOK |
アルカリ電解水の選び方
アルカリ電解水を選ぶときは、まず「pH値」をチェックしましょう。 窓掃除には、pH11以上の強アルカリ性のものが適しています。 パッケージや商品説明に、かならずpH値が記載されているはずです。
つぎに確認したいのが「成分」です。 アルカリ電解水には、電解質として「塩」や「炭酸カリウム」「苛性ソーダ」などがつかわれています。 なかでも「炭酸カリウム」をつかったものは、金属を錆びさせる心配がないのでおすすめです。
選び方のチェックポイント: • pH値が11以上であること • 成分表示が明確であること • 炭酸カリウム使用のものが安全 • スプレーボトル付きが便利 • 詰め替え用があるとコスパが良い
市販のアルカリ電解水には、100円ショップで買えるものから、プロ仕様の高級品まであります。 価格の違いは、主にpH値の高さと、つかわれている電解質の種類によるものです。 初心者なら、まずは中価格帯(500~1,000円程度)のものから始めるとよいでしょう。
マイクロファイバークロスとスクイージー
マイクロファイバークロスは、窓掃除の仕上がりを左右する重要なアイテムです。 極細の繊維が、水分と汚れをしっかりキャッチして、拭き跡を残しません。 普通のタオルとは比べものにならないほど、きれいに仕上がります。
マイクロファイバークロスを選ぶときは、「毛足の長さ」に注目しましょう。 窓掃除には、毛足が短めで、密度の高いものが適しています。 また、色は汚れが見えやすい「白」や「薄い色」がおすすめです。
スクイージーは、窓の水切りに欠かせない道具です。 プロの清掃業者も必ずつかっている、窓掃除の必需品といえるでしょう。 選ぶときは、「ゴムの質」と「持ち手の長さ」がポイントになります。
スクイージー選びのポイント:
• ゴムが柔らかく、窓にフィットするもの
• 幅は30cm程度が使いやすい
• 持ち手が握りやすい形状
• ゴム部分が交換できるタイプがお得
• 初心者は軽量タイプがおすすめ
掃除前の準備と注意点

窓掃除を始める前に、いくつか準備しておくことがあります。 この準備をしっかりすることで、掃除の効率が格段にアップします。 また、安全面での注意点も確認しておきましょう。
掃除前の準備チェックリスト: □ 天気予報を確認(風の強い日は避ける) □ カーテンを外すか、しっかり束ねる □ 窓の近くの物を移動させる □ 床に新聞紙やビニールシートを敷く □ 換気のために、他の窓を開ける □ 掃除道具をすべて手の届く場所に置く
とくに重要なのが「天気」の確認です。 風の強い日は、せっかく掃除してもすぐに汚れがついてしまいます。 理想的なのは、風のない曇りの日か、夕方の時間帯です。
| 天候 | 窓掃除への適性 | 理由 |
|---|---|---|
| 晴れ(日中) | △ | 水分が早く乾きすぎて拭き跡が残る |
| 曇り | ◎ | 適度に乾燥して作業しやすい |
| 雨 | × | 掃除してもすぐ汚れる |
| 風が強い日 | × | ホコリが舞って再付着する |
安全面では、高い場所の窓を掃除するときは、必ず安定した脚立をつかいましょう。 また、アルカリ電解水は目に入ると危険なので、上を向いてスプレーするのは避けてください。 肌が弱い方は、念のためゴム手袋を着用することをおすすめします。
アルカリ電解水を使った窓掃除の基本手順

効率的な掃除の順番(網戸→サッシ→窓ガラス)
窓掃除で失敗しないためには、「掃除の順番」がとても重要です。 多くの人が窓ガラスから掃除を始めてしまいますが、これは大きな間違い。 正しい順番は「網戸→サッシ→窓ガラス」です。
なぜこの順番が大切なのか、理由を説明しましょう。 網戸には、外からのホコリや砂がたくさんついています。 先に窓ガラスを掃除しても、網戸の汚れが風で飛んできて、また汚れてしまうのです。
効率的な掃除の流れ:
- 網戸の汚れを落とす(両面)
- サッシの溝のゴミを取り除く
- サッシにアルカリ電解水をスプレー
- 窓ガラスの内側を掃除
- 窓ガラスの外側を掃除
- 最後に全体をチェック
この順番を守ることで、二度手間を防ぎ、効率よく掃除ができます。 とくに、サッシにあらかじめアルカリ電解水をスプレーしておくのがポイント。 窓ガラスを掃除している間に、汚れが浮いて落としやすくなります。
窓ガラスの掃除方法【3ステップ】
ステップ1:アルカリ電解水でコの字拭き
窓ガラスの掃除は、「コの字型」に拭くのが基本です。 これは、プロの清掃業者も実践している、もっとも効率的な拭き方。 クルクルと円を描いて拭くと、拭きムラができやすいので避けましょう。
まず、タオルにアルカリ電解水を5回ほどスプレーします。 タオル全体が湿る程度が目安で、びしょびしょにする必要はありません。 そして、窓ガラスの左上の角からスタートします。
コの字拭きの手順:
- 左上から右へ、横にまっすぐ拭く
- 右端まで来たら、10cmほど下にずらす
- 右から左へ、横にまっすぐ拭く
- 左端まで来たら、また10cmほど下にずらす
- これを窓の下まで繰り返す
タオルの面が汚れてきたら、きれいな面に折り返してつかいます。 常にきれいな面で拭くことで、汚れの再付着を防げます。 力を入れすぎず、軽いタッチで拭くのがコツです。
| 拭き方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コの字型 | 拭きムラが少ない | 慣れが必要 |
| 円を描く | 簡単 | 拭きムラができやすい |
| 縦・横別々 | 確実 | 時間がかかる |
ステップ2:スクイージーで水切り
アルカリ電解水で汚れを浮かせたら、次はスクイージーで水切りです。 この工程が、窓掃除の仕上がりを大きく左右します。 スクイージーの使い方をマスターすれば、プロ並みの仕上がりが可能です。
スクイージーは、窓の上端にゴム部分をピッタリとあてます。 そして、まっすぐ下に向かって、一気に引き下ろします。 このとき、途中で止まらずに、一番下まで一気に引くのがポイントです。
スクイージーの正しい使い方:
- 窓の左上の角にスクイージーをあてる
- ゴムが窓に密着していることを確認
- まっすぐ下に引き下ろす
- 下まで来たら、ゴムについた水を雑巾で拭き取る
- 5cmほど重ねて、次の列を水切りする
ここで重要なのが、「5cm重ね」のテクニックです。 前の列と5cmほど重ねることで、水滴の取り残しがなくなります。 また、スクイージーのゴムについた水は、毎回必ず拭き取りましょう。
ステップ3:仕上げ拭きのコツ
スクイージーで水切りをしても、窓の四隅には水滴が残ります。 この水滴を、マイクロファイバークロスできれいに拭き取るのが最後の仕上げ。 ここを丁寧にやるかどうかで、仕上がりに大きな差が出ます。
仕上げ拭きは、「上→左右→下」の順番で行います。 まず上部の水滴を横に拭き取り、次に左右の端を縦に拭きます。 最後に下部を横に拍き取って完成です。
仕上げ拭きのポイント:
• マイクロファイバークロスは乾いた状態でつかう
• 軽いタッチで素早く拭く
• 水滴が乾く前に拭き取る
• 拭き終わったらすぐに次の窓へ
• 最後に離れて全体をチェック
プロの技として、仕上げに「新聞紙」をつかう方法もあります。 新聞紙のインクが、ガラスにツヤを与える効果があるのです。 ただし、手が汚れるので、好みで選んでください。
内側と外側で異なる掃除のポイント

窓ガラスの内側と外側では、汚れの種類が違うため、掃除方法も少し変える必要があります。 内側は比較的汚れが少ないので、アルカリ電解水の量も少なめで大丈夫。 一方、外側は汚れがひどいので、たっぷりとスプレーしましょう。
内側の掃除ポイント:
• アルカリ電解水は少なめにスプレー
• 手垢が多い部分は念入りに
• 結露の跡は上から下へ拭く
• カーテンレールの下は汚れやすい
• 仕上げは特に丁寧に
外側の掃除ポイント:
• アルカリ電解水をたっぷりスプレー
• 汚れがひどい場合は5分ほど放置
• 上から下へ、汚れを落とすイメージで
• 雨だれの跡は横に拭くと落ちやすい
• 排気ガスの汚れは2度拭きも検討
| 項目 | 内側 | 外側 |
|---|---|---|
| 主な汚れ | 手垢、ホコリ | 砂、泥、排気ガス |
| アルカリ電解水の量 | 少なめ | 多め |
| 放置時間 | 不要 | 5分程度 |
| 拭く力加減 | 軽め | やや強め |
また、2階以上の外側の窓は、安全を最優先に考えましょう。 無理をせず、届く範囲だけ掃除するか、プロに依頼することも検討してください。 内側だけでも定期的に掃除すれば、十分きれいに保てます。
網戸とサッシの効果的な掃除方法
エチケットブラシを使った網戸掃除
網戸の掃除は、多くの人が苦手とする作業のひとつです。 網目にホコリが絡まって、なかなか落ちないというお悩みをよく聞きます。 しかし、「エチケットブラシ」をつかえば、驚くほど簡単に網戸がきれいになります。
エチケットブラシとは、洋服のホコリ取りにつかうブラシのこと。 じつは、このブラシが網戸掃除に最適なのです。 ブラシの毛が網目に入り込んで、ホコリを絡め取ってくれます。
エチケットブラシでの網戸掃除手順:
- ブラシを軽く水で濡らす
- 網戸の上から下へ、まっすぐブラシを下ろす
- ブラシが汚れたら、水で洗い流す
- 網戸の隅も忘れずに掃除
- 最後に中性洗剤で仕上げ洗い
このとき、力を入れすぎないことが大切です。 軽くなでるようにブラシを動かすだけで、ホコリがきれいに取れます。 網戸の両面を掃除することも忘れずに。
網戸掃除のコツ: • ブラシは一方向に動かす(往復させない) • 汚れがひどい場合は、アルカリ電解水をスプレー • 網戸は外さなくてもOK • 年に2回程度の掃除で十分 • 掃除後は陰干しがベスト
| 道具 | 効果 | 使いやすさ | コスト |
|---|---|---|---|
| エチケットブラシ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 掃除機 | ○ | △ | ○ |
| 高圧洗浄機 | ◎ | △ | × |
| スポンジ | △ | ○ | ◎ |
サッシの頑固な汚れを落とすテクニック

サッシの溝には、砂やホコリ、時には虫の死骸なども溜まります。 この汚れが雨水と混ざって固まると、なかなか落ちない頑固な汚れになってしまいます。 でも、正しい方法を知っていれば、サッシもピカピカにできます。
まず、サッシの掃除は「乾いた状態」から始めるのが鉄則です。 掃除機で大きなゴミを吸い取ってから、アルカリ電解水をつかいます。 この順番を守ることで、泥状の汚れを作らずに済みます。
サッシ掃除の基本手順:
- 掃除機で砂やホコリを吸い取る
- アルカリ電解水をたっぷりスプレー
- 5~10分ほど放置して汚れを浮かせる
- 古い歯ブラシで溝をこする
- 汚れと水分を雑巾で拭き取る
- 仕上げに乾拭きする
アルカリ電解水を「先にスプレーして放置」するのがポイントです。 この間に窓ガラスの掃除をすれば、時間も有効につかえます。 汚れが浮いてくるので、あとは軽くこするだけでOKです。
ペットボトルブラシの活用法
サッシの細い溝を掃除するのに便利なのが「ペットボトルブラシ」です。 100円ショップでも売っている、ペットボトルに取り付けるタイプのブラシ。 水を出しながらブラシでこすれるので、効率よく汚れが落とせます。
ペットボトルブラシの使い方:
- 500mlのペットボトルに水を入れる
- ブラシを取り付ける
- 軽く押して水を出しながら、溝をこする
- 汚れが浮いてきたら、雑巾で拭き取る
- 最後に乾いた布で水分を取る
このブラシのよいところは、水の量を調節できること。 軽く押せば少量、強く押せば多めの水が出ます。 汚れの程度に合わせて、水量を変えられるのが便利です。
ペットボトルブラシ活用のコツ:
• ブラシは溝の幅に合ったものを選ぶ
• 水の代わりにアルカリ電解水を入れてもOK
• 角の汚れは、ブラシを斜めにあてる
• 終わったらブラシをよく洗って乾燥させる
• 1本あると他の場所の掃除にも使える
細部の汚れ対策
サッシの角や、レールの端など、細かい部分の汚れは見逃しがちです。 しかし、これらの場所こそ、カビの温床になりやすい要注意ポイント。 専用の道具を使って、しっかりと掃除しましょう。
細部の掃除には、「綿棒」や「割り箸」が活躍します。 割り箸の先に、キッチンペーパーを巻き付けて輪ゴムで止めれば、即席の掃除棒の完成。 これにアルカリ電解水を染み込ませて、細かい部分を掃除します。
細部掃除の道具と使い方:
• 綿棒:角の汚れ、ビスの周りなど
• 割り箸+キッチンペーパー:レールの端、隙間など
• 使い古しの歯ブラシ:ゴムパッキンの汚れ
• 爪楊枝:極細の隙間、詰まった汚れ
• マイナスドライバー:固まった汚れをかき出す
| 場所 | 適した道具 | 掃除のコツ |
|---|---|---|
| 角の汚れ | 綿棒 | 回転させながら汚れを絡め取る |
| レールの端 | 割り箸 | 先を斜めにカットすると使いやすい |
| ゴムパッキン | 歯ブラシ | 優しくこする(強くこすると傷む) |
| ビス周り | 綿棒 | アルカリ電解水を多めに |
困った汚れ別の対処法
カビが発生した場合の除去方法

窓周りでもっとも厄介な汚れが「カビ」です。 とくに、結露が発生しやすい冬場は、ゴムパッキンやサッシにカビが生えやすくなります。 カビは見た目が悪いだけでなく、健康にも悪影響を与えるので、早めの対処が必要です。
カビには、アルカリ電解水だけでは効果が薄いことがあります。 そんなときは、「消毒用エタノール」の出番です。 エタノールには強い殺菌効果があり、カビの根まで退治してくれます。
カビ除去の手順:
- 換気をよくする(窓を開ける)
- ゴム手袋とマスクを着用
- 消毒用エタノールを優しくスプレー
- 30分ほど放置する
- ティッシュでそっと拭き取る
- アルカリ電解水で仕上げ拭き
- しっかり乾燥させる
重要なのは、カビをこすらないことです。 こすると、カビの胞子が飛び散って、他の場所に広がる恐れがあります。 エタノールで殺菌してから、そっと拭き取るのが正しい方法です。
カビ予防のポイント: • 結露はこまめに拭き取る • 換気を心がける(1日2回以上) • 除湿器を使用する • カビ防止剤を定期的に塗布 • 窓周りの物を減らして風通しをよくする
水垢・ウロコ汚れへの対応

窓ガラスの外側によく見られる「水垢」や「ウロコ状の汚れ」。 これは、雨水に含まれるミネラル分が蒸発して残ったものです。 アルカリ電解水だけでは落ちにくい、やっかいな汚れのひとつです。
水垢やウロコ汚れは「アルカリ性」の汚れなので、酸性の洗剤が効果的です。 しかし、強い酸性洗剤は窓枠を傷める可能性があるので、使い方には注意が必要。 まずは、アルカリ電解水で落とせるところまで落としてみましょう。
水垢・ウロコ汚れの除去方法:
- アルカリ電解水をたっぷりスプレー
- 10分ほど放置
- マイクロファイバークロスで円を描くようにこする
- 落ちない場合は、メラミンスポンジを使用
- それでも落ちない場合は、専用クリーナーを検討
メラミンスポンジをつかうときは、力を入れすぎないように注意しましょう。 ガラスに細かい傷がつく可能性があります。 水をたっぷり含ませて、優しくこするのがコツです。
| 汚れの程度 | 対処法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽度 | アルカリ電解水のみ | とくになし |
| 中度 | メラミンスポンジ併用 | 力を入れすぎない |
| 重度 | 専用クリーナー | 使用後は水でよく流す |
油膜や頑固な汚れの落とし方
キッチンの窓や、換気扇の近くの窓には「油膜」がつきやすいです。 また、タバコのヤニも、時間が経つと頑固な汚れになります。 これらの汚れは、アルカリ電解水の得意分野です。
油汚れに対しては、アルカリ電解水の「乳化作用」が威力を発揮します。 油を水に溶けやすい状態に変化させて、簡単に拭き取れるようにしてくれるのです。 ポイントは、十分な量をスプレーして、しっかり浸透させること。
頑固な油汚れの落とし方:
- アルカリ電解水をたっぷりスプレー
- キッチンペーパーを貼り付ける(湿布法)
- その上からもう一度スプレー
- 15分ほど放置
- キッチンペーパーごと汚れを拭き取る
- マイクロファイバークロスで仕上げ拭き
この「湿布法」は、プロもよくつかうテクニックです。 アルカリ電解水が乾燥せずに、じっくり汚れに浸透します。 頑固な汚れも、これでほとんど落とせるはずです。
特殊な汚れへの対処法:
• シール跡:アルカリ電解水で湿らせてからスクレーパーで
• ペンキ:専用の剥離剤が必要
• 鳥のフン:乾く前にアルカリ電解水で落とす
• 樹液:アルコールを併用
• 接着剤:温めてから除去
車の窓掃除にも活用!アルカリ電解水の応用

車内の窓ガラス掃除のコツ
車の窓ガラス掃除にも、アルカリ電解水は大活躍します。 とくに、車内の窓は手垢や皮脂汚れがつきやすく、視界を妨げる原因に。 アルカリ電解水なら、これらの汚れも簡単に落とせます。
車内の窓掃除で気をつけたいのは、「スプレーの仕方」です。 直接窓にスプレーすると、ダッシュボードやシートに飛び散る恐れがあります。 必ず、クロスにスプレーしてから拭くようにしましょう。
車内窓掃除の手順:
- エンジンを切って、車内を換気
- マイクロファイバークロスにアルカリ電解水をスプレー
- フロントガラスは助手席側から拭き始める
- 上から下へ、端から端まで丁寧に
- サイドガラスも同様に拭く
- 最後に乾いたクロスで仕上げ拭き
フロントガラスの内側は、意外と汚れています。 とくに、エアコンの吹き出し口付近は、ホコリと油分が混じった汚れがつきやすい場所。 この部分は念入りに掃除しましょう。
車内窓掃除のポイント:
• 小さい窓(サイドミラー等)も忘れずに
• ダッシュボードの映り込みに注意
• 仕上げは必ず乾拭き
• 月1回の掃除で視界良好をキープ
• タバコを吸う車は週1回がおすすめ
| 場所 | 汚れの種類 | 掃除頻度 |
|---|---|---|
| フロントガラス内側 | ホコリ、油膜 | 月1回 |
| サイドガラス | 手垢、皮脂 | 月2回 |
| リアガラス | ホコリ | 月1回 |
| サンルーフ | 樹液、鳥のフン | 随時 |
使用時の注意点(コーティングへの影響)
車の窓ガラスには、撥水コーティングが施されていることがあります。 アルカリ電解水を外側の窓に使用すると、このコーティングを傷める可能性があるので注意が必要です。 基本的に、車の外側の窓には使用しないことをおすすめします。
また、車のボディにアルカリ電解水がつくと、塗装を傷める恐れがあります。 とくに、pH値の高いアルカリ電解水は要注意。 内側の掃除に限定して使用するのが安全です。
車に使用する際の注意事項:
• 外側の窓ガラスには使用しない
• ボディに付着したらすぐに水で流す
• カーナビやオーディオ機器には絶対つけない
• 革製シートへの使用は避ける
• ゴム部分への付着も最小限に
安全に使用できる場所:
• 窓ガラスの内側全般
• プラスチック製の内装パーツ
• 布製シート(シミにならないか目立たない場所でテスト)
• ハンドルやシフトレバー(樹脂製のもの)
• ドアの内側パネル
もし、外側の窓も掃除したい場合は、車専用のガラスクリーナーを使用しましょう。 または、中性洗剤を薄めたものでも代用できます。 大切な愛車を守るためにも、適材適所で洗剤を使い分けることが大切です。
おすすめのアルカリ電解水製品
市販品の選び方とpH値の確認方法
アルカリ電解水を選ぶときは、まず商品ラベルを確認しましょう。 「pH値」「成分」「用途」が明記されているものを選ぶのが基本です。 とくに、pH値は必ずチェックしてください。
pH値の確認方法:
- 商品パッケージの表示を見る
- メーカーのウェブサイトで確認
- 取扱説明書を読む
- 不明な場合は問い合わせる
- pH試験紙で実測することも可能
市販品のなかには、pH値を明記していないものもあります。 そういった製品は避けたほうが無難でしょう。 また、「アルカリイオン水」と書かれていても、掃除用でない場合があるので注意が必要です。
選び方のチェックリスト:
□ pH11以上であること
□ 成分表示が明確であること
□ 掃除用途であることが明記されている
□ スプレーボトル付きまたは別売りがある
□ 詰め替え用が販売されている
□ 使用期限が明記されている
価格については、安すぎるものは避けたほうがよいでしょう。 pH値を高く保つには、それなりの製造コストがかかります。 500mlで300円以下のものは、pH値が低い可能性があります。
安全性と成分について
アルカリ電解水の安全性は、使われている「電解質」によって大きく変わります。 主な電解質には、「塩化ナトリウム(塩)」「炭酸カリウム」「水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)」があります。 それぞれに特徴があるので、用途に合わせて選びましょう。
各電解質の特徴:
• 塩化ナトリウム:安価だが金属を錆びさせる可能性
• 炭酸カリウム:安全性が高く金属も錆びない
• 水酸化ナトリウム:洗浄力は高いが取り扱いに注意
安全に使用するための注意点:
• 必ず換気をしながら使用する
• 目に入らないよう注意する
• 肌が弱い人は手袋を着用
• 他の洗剤と混ぜない
• 子供の手の届かない場所に保管
• 使用後は手を洗う
| 電解質 | 安全性 | 洗浄力 | 金属への影響 |
|---|---|---|---|
| 塩化ナトリウム | ○ | ○ | △(錆びの可能性) |
| 炭酸カリウム | ◎ | ◎ | ◎(影響なし) |
| 水酸化ナトリウム | △ | ◎ | ○ |
アルカリ電解水は、正しく使えば非常に安全な洗剤です。 化学物質を含まないので、環境にもやさしく、排水しても問題ありません。 ただし、強アルカリ性という性質上、取り扱いには十分注意しましょう。
窓掃除を楽にする時短テクニック

最適な掃除のタイミングと天候
窓掃除には、「ベストタイミング」があることをご存知でしょうか。 天候や時間帯を選ぶことで、掃除の効率が格段にアップします。 逆に、タイミングを間違えると、二度手間になることも。
窓掃除に最適な条件は「曇りの日」または「夕方」です。 なぜなら、直射日光が当たると、水分があっという間に乾いてしまい、拭き跡が残りやすくなるから。 また、汚れも見えにくくなり、拭き残しの原因になります。
最適な掃除タイミング:
• 天候:曇りの日がベスト
• 時間:朝の早い時間か夕方
• 季節:春と秋が理想的
• 避けるべき日:風の強い日、雨の日
• 室温:15~25度が作業しやすい
季節でいえば、春と秋がおすすめです。 夏は暑くて水分がすぐ乾き、冬は寒くて手がかじかみます。 過ごしやすい季節に、計画的に掃除をするのが賢い方法です。
月別の窓掃除おすすめ度:
• 1~2月:△(寒くて作業しづらい)
• 3~4月:◎(花粉が落ち着いたら)
• 5~6月:○(梅雨前に)
• 7~8月:△(暑すぎる)
• 9~10月:◎(台風シーズン後)
• 11~12月:○(年末大掃除)
掃除頻度と汚れ防止のコツ

窓掃除を楽にする最大のコツは、「汚れをためないこと」です。 月に1回、軽い掃除をするだけで、いつもきれいな窓を保てます。 逆に、年に1~2回しか掃除しないと、汚れが固着して大変な作業になってしまいます。
理想的な掃除頻度:
• 内側の窓:月1回(さっと拭くだけ)
• 外側の窓:2~3ヶ月に1回
• 網戸:半年に1回
• サッシ:3ヶ月に1回
• 大掃除:年1回(すべて念入りに)
この頻度を守れば、1回の掃除時間は30分程度で済みます。 汚れが軽いうちに対処することで、アルカリ電解水だけで十分きれいになります。 特別な洗剤や道具も必要ありません。
汚れ防止のコツ:
• 結露はこまめに拭き取る
• 換気扇を活用して湿気を逃がす
• カーテンを定期的に洗濯
• 窓の近くで喫煙しない
• 料理中は換気を徹底
• 雨の後は早めに外側を確認
| 対策 | 効果 | 手間 |
|---|---|---|
| 結露を拭く | カビ防止 | 毎日5分 |
| 換気 | 湿気対策 | 1日2回 |
| 撥水スプレー | 汚れ防止 | 年2回 |
| カーテン洗濯 | ホコリ減少 | 月1回 |
プロが実践する効率的な動線

プロの清掃業者は、無駄のない動きで短時間に窓掃除を終わらせます。 その秘密は、「動線」にあります。 効率的な動線を身につければ、あなたも時短掃除が可能になります。
プロの動線の基本は「上から下へ」「奥から手前へ」です。 2階の窓から始めて、1階へ。 家の奥の部屋から始めて、玄関側へ。 この流れで掃除すると、汚れた水が垂れても問題ありません。
効率的な掃除の流れ:
- すべての窓のカーテンを開ける
- 道具を台車やバケツにまとめる
- 2階の奥の部屋から開始
- 1部屋終わったら次の部屋へ
- 1階に降りて同じ流れで
- 最後に玄関の窓で終了
部屋ごとの掃除手順:
- 網戸にアルカリ電解水をスプレー
- サッシにもスプレーして放置
- 窓ガラスの内側を掃除
- 窓ガラスの外側を掃除
- 網戸とサッシを仕上げる
- 道具を持って次の部屋へ
この流れなら、行ったり来たりする無駄がありません。 また、スプレーして放置している間に他の作業ができるので、時間を有効活用できます。 慣れれば、4LDKの家でも2時間程度で全部の窓がきれいになります。
時短のための工夫:
• スプレーボトルは2本用意(詰め替えの手間を省く)
• マイクロファイバークロスは部屋数分用意
• 汚れた道具入れ用のビニール袋を携帯
• タイマーをセット(1部屋15分目安)
• 音楽を聴きながら楽しく作業
お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介
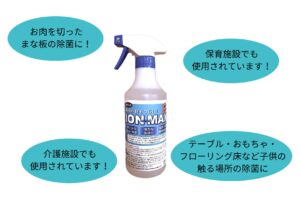
アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。
中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。
マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。
苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。
また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。
マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。
アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。
さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。
pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。
食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。
マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。
優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。
自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。
まとめ
アルカリ電解水をつかった窓掃除について、詳しく解説してきました。 化学物質をつかわない安全な方法で、プロ並みの仕上がりが実現できることがおわかりいただけたでしょうか。
窓掃除のポイントをおさらいすると、「pH11以上のアルカリ電解水を選ぶ」「正しい道具をそろえる」「効率的な手順で掃除する」の3つです。 とくに、掃除の順番(網戸→サッシ→窓ガラス)と、コの字型の拭き方は、ぜひマスターしてください。
最後に、窓掃除は「こまめに」が鉄則です。 月1回、30分程度の軽い掃除を続けることで、いつもピカピカの窓を保てます。 アルカリ電解水という強い味方を手に入れたあなたなら、もう窓掃除は怖くありません。
さあ、今日からあなたも窓掃除マスターです。 アルカリ電解水を片手に、家中の窓をピカピカにしてみませんか。 きれいな窓から差し込む光は、きっとあなたの心も明るくしてくれるはずです。