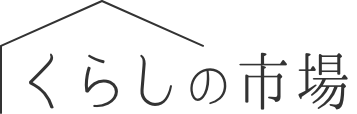「肉を切ったまな板は絶対に除菌しないといけない?」と不安に感じている人はいませんか?
結論からいうと、肉を切ったまな板には除菌が必要です。ではどのような除菌方法が適しているのでしょうか。
この記事では、肉を切ったまな板に除菌が必要な理由や除菌方法についてお伝えします。
除菌方法の選び方も紹介しますので、まな板除菌にお悩みの方はぜひ参考にしてくださいね。
目次
肉を切ったまな板には除菌が必要!洗剤だけでは不十分?

生肉を切ったまな板には、肉についている菌が付着します。
肉に付着している菌とは、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌、サルモネラなど。どれも食中毒を引き起こす菌です。
これらの菌は、生肉を食べること以外に、まな板を介してほかの食材に付着することでも食中毒を引き起こしてしまいます。そのため、まな板を常に清潔にしておくことが必要です。
生肉からまな板に付着した菌は、水で洗い流すだけでは取り除けません。なぜなら、水だけでは肉の脂を落としきれないため、残った部分から菌が繁殖してしまうからです。
では洗剤で洗えば十分なのでしょうか。とあるまな板の洗浄実験によると、洗剤で洗うだけでも菌を減らせることが明らかになりました。しかし完全に取り除くことは難しく、菌が残ってしまうケースもあったとのこと。
このことから以下のようなことがいえるでしょう。
- 肉を切ったまな板には、洗剤による洗浄が必須であること
- 洗剤による洗浄だけでは菌が残ってしまうケースもあり、十分とはいえないこと
「少しくらい菌が残っても大丈夫なのでは?」と思うかもしれません。しかし、実は少量の菌でも食中毒を引き起こしてしまう恐れがあります。食中毒を引き起こさないためには、菌を徹底的に取り除く必要があるのです。
肉を切ったまな板の除菌方法4選

肉を切ったまな板は、使用後すぐに洗剤と流水でしっかりと洗います。使用した面だけでなく、裏側や側面も丁寧に洗浄することが大切です。その後、除菌のステップへと進みましょう。
まな板に効果的な除菌方法には以下の4種類があります。
- アルカリ電解水をスプレーする
- アルコールをスプレーする
- 熱湯をかける
- 塩素系漂白剤にひたす・スプレーする
それぞれについて使い方や特徴を紹介します。
アルカリ電解水をスプレーする
アルカリ電解水とは、水を電気分解して得られた、機能性のある水のこと。たんぱく質や油脂を分解する力があります。
市販されているアルカリ電解水は、pH11~12.5程度のものが多くみられます。中でもpH12.5のアルカリ電解水は優れた除菌効果があるため、まな板除菌におすすめです。
【アルカリ電解水による除菌方法】
- 洗剤と流水で汚れを洗い流したまな板の表面・裏面に、アルカリ電解水をスプレーする
- 30秒程度放置する
- 流水で洗い流し、乾燥させる
アルコールをスプレーする
感染症予防などで日常的に使っている人も多いアルコール。高い除菌力をもっており、まな板の除菌剤としても優秀です。
アルコールは、腸管出血性大腸菌やサルモネラなど食中毒を引き起こす多くの菌に効果があります。ただし、アルコールが効かないタイプの菌も存在しますので、知っておきましょう。
【アルコールによる除菌方法】
- 洗剤と流水でまな板の汚れを洗い流し、清潔なふきんなどで水分を拭き取る
- まな板の表面・裏面にアルコールをスプレーする
- 乾燥させる
まな板に水分が残っていると、アルコールの除菌力が弱まってしまいます。洗浄後には水分をしっかりと拭きとってから、アルコールをスプレーしましょう。
熱湯をかける

食中毒の原因となる菌の多くは熱湯をかけることで死滅するため、熱湯をまな板にかける方法は除菌に効果的です。
しかし、家庭で行う際には難しい点もあります。たとえば、まな板に熱湯を均一にかけるのが難しいことや、シンクに熱湯がかかることでシンクが傷みやすくなってしまうことなどがあげられます。
また、熱湯によるやけどのリスクもありますので、子どものいる家庭などではいっそうの注意が必要でしょう。
【熱湯による除菌方法】
- 洗剤と流水で洗ったまな板の表面と裏面に、熱湯をたっぷりかける
- 風通しの良い場所にまな板を立てかけて置き、冷ましながら乾燥させる
肉を切ったまな板に直接熱湯をかけてしまうと、たんぱく質が固まってしまい、汚れが落ちにくくなってしまいます。熱湯を使って除菌をするときには、あらかじめまな板を丁寧に洗っておきましょう。
塩素系漂白剤に浸す・スプレーする
塩素系漂白剤には高い除菌力・殺菌力・漂白力があります。まな板の除菌だけでなく、黄ばみや黒ずみなどが気になる場合にも便利です。
ただし、塩素系漂白剤には強い刺激があります。直接手肌に付着しないよう、使用時にはゴム手袋を使いましょう。
塩素系漂白剤には、コスパの良い「液体タイプ」と、より簡単に使える「スプレータイプ」の2種類があります。
【液体タイプの塩素系漂白剤による除菌方法】
- 洗剤と流水で洗ったまな板全体をふきんで覆う
- ふきんの上から塩素系漂白剤(希釈する必要があれば薄めたもの)をかける
- 漂白剤の表示に合わせて、しばらく放置する
- しっかりとすすぐ
【スプレータイプの塩素系漂白剤による除菌方法】
- 洗剤と流水で洗ったまな板全体に塩素系漂白剤をスプレーする
- 漂白剤の表示に合わせて、しばらく放置する
- しっかりとすすぐ
塩素系漂白剤は少量でも口に入ると危険です。どちらのタイプを使うにしても、塩素系漂白剤が残らないようにしっかりとすすぎましょう。
除菌方法を選ぶときの4つのポイント

上記4つの除菌方法のうち、どの方法を選べばよいのでしょうか。
ここからは、以下の4点にフォーカスして除菌方法の選び方をお伝えします。
- 使いやすさ
- 安全性
- まな板の素材との相性
- 用途範囲
これらの観点から、自分に合うまな板の除菌方法を見つけてくださいね。
使いやすさ
まな板の除菌方法は、除菌剤の使い勝手で選びましょう。
まな板の除菌は日常的に行うことが必要です。使い勝手が悪いと除菌作業が面倒になってしまうことも考えられますので、自分が使いやすいと思う除菌剤を使うのがよいでしょう。
素手で使えるという点においては、アルカリ電解水やアルコールが便利です。熱湯による除菌も素手で行えますが、熱湯が手に散らないように注意しましょう。
また、においが気にならないという点においては、アルカリ電解水と熱湯がおすすめです。アルコールや塩素系漂白剤は独特のにおいがしますので、においに敏感な人には不向きかもしれません。
安全性
除菌剤は、口に入れる食品を直接のせるまな板に使うもの。その安全性についても知っておきましょう。
さきほど紹介した4つのうち、安全性が高いのはアルカリ電解水とアルコール、熱湯の3つです。
アルカリ電解水の原料は水です。また、まな板除菌に使うアルコールは、食品のアルコールに食品添加物を加えて作られています。これらのことから、アルカリ電解水とアルコールは安全性が高いことがわかります。
熱湯は水そのものなので安全です。しかし、まな板にかけるときにやけどをしてしまうリスクがあります。使用中の安全性を考えると、熱湯による除菌は安全性が高いとはいえないかもしれません。
安全性の観点で考えると、塩素系漂白剤には注意が必要です。少量でも口に入ってしまうと危険ですし、手肌に付着すると皮膚がただれてしまうことも知られています。
まな板の素材との相性

まな板の除菌方法を選ぶときには、まな板の素材にも注目しましょう。
プラスチック製のまな板の場合は、前述した4つの方法がすべて使えます。
一方、木製のまな板には塩素系漂白剤が使えません。また熱の影響でまな板が変形する恐れがあるため、熱湯による除菌ができない場合もあります。熱湯による除菌が可能かどうかは、まな板の説明書などであらかじめ確認しておきましょう。
用途範囲
まな板の除菌方法を検討するとき、除菌剤の用途範囲についても考えてみてはいかがでしょうか。
前述の除菌方法で使う除菌剤のうち、広範囲で使えるのはアルカリ電解水です。
アルカリ電解水は洗浄力も優れているため、手垢や油汚れなどの掃除にも使えます。家庭で発生する汚れの大半はアルカリ電解水で落とせるので、常備しておくと重宝するでしょう。
アルコールもさまざまな部分の除菌に使える便利な除菌剤です。しかし、汚れに対する洗浄力はそれほどありません。除菌を目的とした使い方がメインとなるでしょう。
塩素系漂白剤は、ふきんや食器などの除菌・漂白・消臭に効果的。液体を希釈すれば、ドアノブなどの除菌にも使えます。しかし金属製品には使えないなど、強力さゆえに使い道が限られてしまいます。
【まとめ】肉を切ったまな板にはアルカリ電解水での除菌がおすすめ
肉を切ったまな板は、水で洗い流すだけではきれいになりません。使用後すぐに、洗剤と流水で丁寧に洗いましょう。
洗浄だけでも菌をある程度洗い流せますが、より安心してまな板を使うためには除菌が必要です。
以下に、この記事で紹介した除菌方法をまとめました。
|
|
使いやすさ |
安全性 |
まな板の素材との相性 |
用途範囲 |
|
アルカリ電解水 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
|
アルコール |
〇 |
◎ |
◎ |
○ |
|
熱湯 |
〇 |
〇 |
△ |
― |
|
塩素系漂白剤 |
△ |
△ |
△ |
△ |
すべての項目で高評価のアルカリ電解水には、以下のような特徴があります。
- 除菌効果が高い
- 素手で使える
- においがない
- 安全性が高い
- どんな素材のまな板にも使える
- 家中の掃除にも使える
肉を切ったまな板の除菌方法で迷ったときには、ぜひアルカリ電解水を試してみてください。