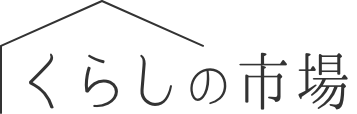「アルカリ電解水で掃除したら、お気に入りの服が色落ちしてしまった」「革製品に使ったら変色してしまって困っている」このような経験はありませんか?
環境にやさしく、界面活性剤を使わない洗浄剤として注目を集めるアルカリ電解水ですが、実は使い方を間違えると大切な衣類や家具を傷めてしまうリスクがあります。
本記事では、アルカリ電解水による色落ちを防ぎながら、その優れた洗浄力を最大限に活用する方法を詳しく解説します。
色落ちしやすい素材の見分け方から、安全な希釈方法、プロが実践する使い方まで、すぐに実践できる情報をお届けします。
目次
アルカリ電解水とは?色落ちのリスクと基本知識

アルカリ電解水は、水を電気分解することで生成される強アルカリ性の洗浄水です。
その高い洗浄力から、家庭での掃除や洗濯、プロの清掃現場まで幅広く活用されています。
しかし、この強力な洗浄力こそが、色落ちのリスクにもつながっているのです。
アルカリ電解水の成分と特徴
アルカリ電解水の主成分は、99%以上が純水です。
残りのわずかな成分として、炭酸カリウムや塩化ナトリウムなどの電解質が含まれています。
これらの電解質によって、通常の水とは異なる特殊な性質を持つようになるのです。
アルカリ電解水の最大の特徴は、マイナスイオンを豊富に含んでいることです。
このマイナスイオンが汚れの粒子に浸透し、汚れと素材の間に入り込むことで、汚れを浮かせて落とします。
また、油脂やたんぱく質を分解する力も持っているため、皮脂汚れや食べこぼしなどの頑固な汚れにも効果を発揮します。
アルカリ電解水の特徴をまとめると:
• 成分の99%以上が純水で安全性が高い
• 界面活性剤を含まないため、すすぎが簡単
• マイナスイオンの力で汚れを浮かせる
• 油脂やたんぱく質を分解する力がある
• 除菌・消臭効果も期待できる
ただし、この強力な洗浄力が、染料と繊維の結合を弱めることがあり、それが色落ちの原因となります。
特に天然染料で染められた製品や、染色が不十分な素材では、色落ちのリスクが高まります。
pH値による洗浄力の違い
アルカリ電解水の洗浄力は、pH値によって大きく変わります。
pH値とは、水素イオン濃度を表す指標で、7を中性として、それより高い数値がアルカリ性、低い数値が酸性を示します。
一般的なアルカリ電解水のpH値は11.5から13.5の範囲にあり、これは強アルカリ性に分類されます。
pH値が高いほど洗浄力は強くなりますが、同時に素材への影響も大きくなります。
具体的には、pH12以上のアルカリ電解水は、たんぱく質や油脂を強力に分解する反面、染料の結合も弱める可能性があります。
以下は、pH値による洗浄力と用途の目安です:
| pH値 | 洗浄力 | 適した用途 | 色落ちリスク |
|---|---|---|---|
| 11.0~11.5 | 弱 | 軽い汚れ、デリケート素材 | 低 |
| 11.5~12.0 | 中 | 日常的な掃除、洗濯 | 中 |
| 12.0~12.5 | 強 | 頑固な汚れ、油汚れ | 高 |
| 12.5以上 | 最強 | 業務用、特殊清掃 | 非常に高 |
色落ちを防ぐためには、使用する素材に応じてpH値を調整することが重要です。
デリケートな衣類には、pH11.5以下に希釈したアルカリ電解水を使用することをおすすめします。
界面活性剤不使用のメリット

アルカリ電解水の大きな魅力は、界面活性剤を使用していないことです。
界面活性剤は、水と油を混ぜ合わせる働きを持つ成分で、一般的な洗剤には必ず含まれています。
しかし、界面活性剤には素材に残留しやすいという欠点があります。
アルカリ電解水は界面活性剤を使わずに、アルカリ性の力だけで汚れを落とします。
そのため、すすぎが1回で済み、水の使用量を大幅に削減できます。
また、洗剤残りによる肌トラブルのリスクも軽減されます。
界面活性剤不使用によるメリット:
• すすぎ回数を減らせるため、水道代の節約になる
• 洗剤残りによる肌荒れやアレルギーのリスクが低い
• 環境への負荷が少ない
• 乾燥後に白い粉が残らない
• 赤ちゃんや敏感肌の方でも安心して使える
ただし、界面活性剤がないということは、汚れを包み込んで再付着を防ぐ力が弱いということでもあります。
そのため、アルカリ電解水で洗濯する際は、汚れがひどい部分を先に処理してから全体を洗うなど、使い方に工夫が必要です。
色落ちしやすい素材・アイテムの見分け方

アルカリ電解水を安全に使用するためには、色落ちしやすい素材を正しく見分けることが重要です。
素材の種類や染色方法によって、色落ちのリスクは大きく異なります。
ここでは、特に注意が必要な素材について詳しく解説します。
天然繊維の色落ちリスク
天然繊維は、その構造上、アルカリ電解水の影響を受けやすい特徴があります。
特に動物性繊維と植物性繊維では、色落ちのメカニズムが異なるため、それぞれに適した対処法が必要です。
天然繊維の染料は、化学繊維に比べて繊維との結合が弱い傾向があります。
シルク・ウールなど動物性繊維
シルクやウールなどの動物性繊維は、アルカリ電解水に対して最も注意が必要な素材です。
これらの繊維は、たんぱく質で構成されているため、アルカリ性の物質によって構造が変化しやすいのです。
シルクの場合、pH9以上のアルカリ性溶液に触れると、繊維表面のセリシンというたんぱく質が溶け出します。
この過程で、染料も一緒に流れ出してしまい、色落ちや変色が起こります。
また、繊維自体が傷んで、独特の光沢が失われることもあります。
ウールも同様に、アルカリ性に弱い性質を持っています。
ウールの表面にあるスケールという鱗状の組織が、アルカリ電解水によって開いてしまい、染料が流出しやすくなります。
さらに、繊維が縮んだり、フェルト化したりする恐れもあります。
動物性繊維の取り扱い注意点:
• シルク製品にはアルカリ電解水を直接使用しない
• ウール製品は必ず10倍以上に希釈して使用する
• 色物は特に注意し、事前にテストを行う
• 使用する場合は短時間で処理する
• 中性洗剤での洗濯を推奨
綿・麻など植物性繊維の注意点
綿や麻などの植物性繊維は、動物性繊維に比べてアルカリ性に強い特徴があります。
しかし、だからといって安心してはいけません。
染色方法や加工によっては、色落ちのリスクが高い場合があります。
綿は本来、アルカリ性に対して比較的安定した素材です。
むしろ、アルカリ性の環境下では繊維が膨潤し、汚れが落ちやすくなるというメリットもあります。
ただし、反応染料で染められた濃色の綿製品は、アルカリ電解水によって色落ちする可能性があります。
麻も綿と同様に、アルカリ性には比較的強い素材です。
しかし、麻独特の風合いを出すために施された加工が、アルカリ電解水によって損なわれることがあります。
特に、柔軟加工や撥水加工が施された麻製品は注意が必要です。
植物性繊維使用時のポイント:
• 白物は問題なく使用できることが多い
• 濃色のものは必ず色落ちテストを実施
• デニムなどインディゴ染めは特に注意
• 草木染めなどの天然染料は使用を避ける
• プリント部分は変色の可能性がある
合成繊維と色落ちの関係
合成繊維は一般的に、天然繊維よりもアルカリ電解水に対して安定しています。
ポリエステル、ナイロン、アクリルなどの合成繊維は、化学的に安定した構造を持っているため、アルカリ性の影響を受けにくいのです。
しかし、完全に安全というわけではありません。
ポリエステルは最もアルカリ性に強い合成繊維です。
pH13程度の強アルカリ電解水でも、繊維自体が損傷することはほとんどありません。
ただし、分散染料で染められたポリエステルは、高温のアルカリ性溶液で色落ちすることがあります。
ナイロンは、ポリエステルに次いでアルカリ性に強い素材です。
しかし、長時間の浸漬や高濃度のアルカリ電解水の使用は避けるべきです。
特に、ストッキングなどの薄手のナイロン製品は、繊維が劣化しやすいので注意が必要です。
合成繊維の特性一覧:
| 素材 | アルカリ耐性 | 色落ちリスク | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル | 非常に高い | 低 | 高温時は注意 |
| ナイロン | 高い | 低~中 | 長時間浸漬は避ける |
| アクリル | 中 | 中 | 毛玉ができやすい |
| ポリウレタン | 低 | 高 | 劣化しやすい |
レザー製品・革製品への影響
レザー製品は、アルカリ電解水の使用を避けるべき代表的な素材です。
革は動物の皮をなめし加工したもので、たんぱく質が主成分となっています。
アルカリ性の物質は、このたんぱく質を分解し、革の構造を破壊してしまいます。
革製品にアルカリ電解水を使用すると、表面の保護膜が溶け出し、色落ちや変色が起こります。
また、革が硬くなったり、ひび割れたりすることもあります。
特に、植物タンニンでなめされた革は、アルカリ性に弱い傾向があります。
スエードやヌバックなどの起毛革は、さらにデリケートです。
これらの素材は表面積が大きいため、アルカリ電解水の影響を受けやすく、一度ダメージを受けると修復が困難です。
色落ちだけでなく、風合いも大きく損なわれてしまいます。
革製品の取り扱い:
• アルカリ電解水は絶対に使用しない
• 革専用クリーナーを使用する
• 水拭きも最小限に留める
• 定期的に保革剤でメンテナンスする
• 汚れがひどい場合は専門店に相談する
染色方法による色落ちの違い
染色方法によって、色落ちのしやすさは大きく異なります。
一般的に、繊維の内部まで染料が浸透している「先染め」は色落ちしにくく、表面だけを染めた「後染め」は色落ちしやすい傾向があります。
また、使用される染料の種類も重要な要因です。
反応染料は、繊維と化学的に結合するため、比較的色落ちしにくい染料です。
綿や麻などの植物性繊維によく使用されます。
しかし、アルカリ性が強すぎると、この結合が切れて色落ちすることがあります。
直接染料は、繊維に物理的に吸着するだけなので、色落ちしやすい染料です。
絹や羊毛の染色によく使われますが、アルカリ電解水の使用は避けるべきです。
特に、鮮やかな色ほど色落ちのリスクが高くなります。
染色方法別の色落ちリスク:
| 染色方法 | 色落ちリスク | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 先染め | 低 | 糸の段階で染色 | 高級品に多い |
| 後染め | 高 | 製品になってから染色 | 安価な製品に多い |
| プリント | 非常に高 | 表面のみ着色 | 摩擦にも弱い |
| 草木染め | 非常に高 | 天然染料使用 | アルカリ厳禁 |
アルカリ電解水が使えない素材と代替方法

アルカリ電解水は万能ではありません。
使用してはいけない素材を正しく理解し、適切な代替方法を知ることで、大切な品物を守ることができます。
ここでは、使用NGな素材と、それぞれに適した代替洗浄方法を詳しく解説します。
使用NGな素材リスト
アルカリ電解水を使用できない素材は、意外と身の回りに多く存在します。
これらの素材にアルカリ電解水を使用すると、変色、腐食、劣化などの深刻なダメージを与える可能性があります。
事前に素材を確認し、適切な判断をすることが重要です。
アルミニウム・真鍮・銅などの金属類
アルミニウムは、アルカリ性に非常に弱い金属です。
アルカリ電解水に触れると、表面の酸化被膜が溶け出し、白く変色したり、腐食が進行したりします。
キッチンのアルミ鍋や、窓のアルミサッシなどは特に注意が必要です。
真鍮や銅も同様に、アルカリ性によって腐食されやすい金属です。
これらの金属は、アルカリ電解水と反応して緑青(ろくしょう)と呼ばれる青緑色の錆を生じます。
アンティーク家具の金具や、楽器の部品などによく使われているため、注意が必要です。
金属類への影響:
• アルミニウム:白色の腐食生成物が発生
• 真鍮・銅:緑青が発生し、光沢が失われる
• 亜鉛メッキ:メッキ層が剥離する
• ステンレス:一般的には問題ないが、長時間は避ける
• 鉄:防錆処理がない場合は錆びやすくなる
これらの金属製品を掃除する場合は、中性洗剤や専用クリーナーを使用しましょう。
特に、金属の種類が不明な場合は、アルカリ電解水の使用を避けることが賢明です。
漆器・木製家具・大理石
漆器は、日本の伝統工芸品として大切に扱われるべき素材です。
漆の塗膜は、アルカリ性によって軟化し、剥離する恐れがあります。
また、漆の美しい光沢が失われ、修復が困難になることもあります。
木製家具も、アルカリ電解水の使用には適していません。
特に、無垢材やオイル仕上げの家具は、アルカリ性によって木材の成分が溶出し、シミや変色の原因となります。
ニスやラッカーなどの塗装も、アルカリ性で軟化や剥離を起こす可能性があります。
大理石は、主成分が炭酸カルシウムであるため、アルカリ性には比較的強い素材です。
しかし、長時間の接触や高濃度のアルカリ電解水は、表面の光沢を失わせる原因となります。
また、大理石の模様が薄くなることもあります。
天然素材の取り扱い:
| 素材 | 影響 | 代替方法 |
|---|---|---|
| 漆器 | 塗膜の軟化・剥離 | 柔らかい布で乾拭き |
| 無垢材 | シミ・変色 | 専用オイルでメンテナンス |
| 大理石 | 光沢の喪失 | 大理石専用クリーナー |
| 竹・籐 | 変色・劣化 | 固く絞った布で水拭き |
アクリル樹脂・ゴム素材
アクリル樹脂は、透明度が高く、ガラスの代替品として広く使用されています。
しかし、アルカリ性に弱く、白く濁ったり、ひび割れたりすることがあります。
水槽や展示ケース、照明カバーなどに使われているため、掃除の際は注意が必要です。
ゴム素材も、アルカリ電解水によって劣化しやすい素材です。
天然ゴムは特に影響を受けやすく、硬化や亀裂の原因となります。
合成ゴムも種類によっては、膨潤や軟化を起こすことがあります。
樹脂・ゴム製品の注意点:
• アクリル板:曇りや細かいひび割れが発生 • ポリカーボネート:強度が低下する • 天然ゴム:硬化して弾力性を失う • シリコンゴム:比較的耐性があるが長時間は避ける • ゴムパッキン:劣化が早まり、密閉性が低下
これらの素材には、中性洗剤を薄めた溶液や、専用クリーナーを使用することをおすすめします。
特に、透明な樹脂製品は、アルコール系のクリーナーも避けるべきです。
液晶画面・コーティング製品
液晶画面は、現代生活に欠かせない製品ですが、非常にデリケートな構造をしています。
画面表面には反射防止コーティングや指紋防止コーティングが施されており、アルカリ電解水はこれらのコーティングを溶かしてしまいます。
コーティングが損傷すると、画面が見づらくなるだけでなく、修復も困難です。
メガネのレンズも同様に、各種コーティングが施されています。
反射防止コーティング、UVカットコーティング、撥水コーティングなどは、アルカリ性によって剥がれたり、変質したりします。
一度損傷したコーティングは元に戻せません。
コーティング製品の取り扱い:
• 液晶画面:専用クリーナーか、マイクロファイバークロスで乾拭き • メガネレンズ:メガネ専用クリーナーを使用 • カメラレンズ:レンズクリーニング液とクロスで清掃 • 車のガラスコーティング:中性のカーシャンプーを使用 • フッ素コーティング製品:メーカー推奨の方法で清掃
素材別の代替洗浄方法
アルカリ電解水が使えない素材でも、適切な方法を選べば、きれいに掃除することができます。
素材の特性を理解し、それぞれに最適な洗浄方法を選ぶことが、品物を長持ちさせる秘訣です。
金属製品の場合、素材に応じた専用クリーナーを使用しましょう。
アルミニウム製品には、クエン酸を薄めた溶液が効果的です。
真鍮や銅製品は、市販の金属磨き剤で光沢を取り戻すことができます。
ステンレスは、重曹ペーストで優しく磨くと良いでしょう。
木製家具や漆器は、基本的に乾拭きが原則です。
汚れがひどい場合は、固く絞った布で軽く拭き、すぐに乾いた布で水分を取り除きます。
定期的なワックスがけやオイル塗布で、美しさを保つことができます。
代替洗浄方法の一覧:
| 素材カテゴリー | 推奨洗浄方法 | 使用する洗剤・道具 |
|---|---|---|
| 金属類 | 素材別専用クリーナー | クエン酸、重曹、金属磨き |
| 木製品・漆器 | 乾拭き中心 | マイクロファイバークロス |
| 天然石 | 専用クリーナー | 大理石用洗剤 |
| 樹脂・ゴム | 中性洗剤 | 食器用洗剤を希釈 |
| コーティング製品 | 専用品使用 | 各製品専用クリーナー |
これらの代替方法を使用する際も、必ず目立たない部分でテストを行い、素材への影響を確認してから全体に使用しましょう。
また、メーカーの取扱説明書がある場合は、それに従うことが最も安全です。
色落ちを防ぐアルカリ電解水の希釈方法

アルカリ電解水を安全に使用するためには、適切な希釈が不可欠です。
用途や素材に応じて濃度を調整することで、洗浄力を保ちながら色落ちのリスクを最小限に抑えることができます。
ここでは、実践的な希釈方法を詳しく解説します。
用途別の推奨希釈倍率
アルカリ電解水の希釈倍率は、汚れの程度と素材の耐性によって決定します。
一般的に、汚れが軽いほど、また素材がデリケートなほど、高い希釈倍率が必要です。
プロの清掃現場では、この希釈倍率の調整が作業の成否を左右します。
衣類のしみ抜き(10倍希釈)
衣類のしみ抜きには、10倍希釈のアルカリ電解水が最適です。
この濃度は、十分な洗浄力を保ちながら、繊維へのダメージを最小限に抑えることができます。
原液100mlに対して水900mlを加えることで、10倍希釈液を作ることができます。
10倍希釈液のpH値は約11.5となり、これは一般的な洗濯用洗剤と同程度のアルカリ度です。
食べこぼしや皮脂汚れなどの日常的なしみには、この濃度で十分な効果が得られます。
ただし、血液やワインなどの特殊なしみには、別の処理が必要な場合があります。
衣類のしみ抜き手順:
• スプレーボトルに10倍希釈液を入れる
• しみの裏側に白い布を当てる
• 表側から希釈液をスプレーする
• 清潔な布で軽く叩いて汚れを移す
• 水で十分にすすぐ
色物の衣類の場合は、さらに薄い15倍希釈から始めることをおすすめします。
特に、濃色のデニムや黒い衣類は、色落ちしやすいため注意が必要です。
絨毯・カーペット(10倍希釈)
絨毯やカーペットの清掃にも、10倍希釈のアルカリ電解水が適しています。
これらの素材は、構造が複雑で汚れが入り込みやすいため、ある程度の洗浄力が必要です。
同時に、色落ちや素材の劣化を防ぐ配慮も欠かせません。
カーペットの材質によって、適切な処理方法が異なります。
ウール製のカーペットは、動物性繊維であるため、使用前に必ず目立たない部分でテストを行いましょう。
合成繊維のカーペットは比較的安全ですが、接着剤や裏地の素材にも注意が必要です。
カーペット清掃のポイント:
| 工程 | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 前処理 | 掃除機で表面のゴミを除去 | 濡れる前に必ず実施 |
| スプレー | 全体に均等に噴霧 | 濡らしすぎない |
| ブラッシング | 柔らかいブラシで汚れを浮かす | 強くこすらない |
| 吸い取り | 乾いたタオルで水分を除去 | 色移りを確認 |
| 乾燥 | 十分に換気して自然乾燥 | カビ防止のため完全に乾かす |
車内清掃(5~20倍希釈)
車内清掃では、汚れの程度や清掃箇所によって、5倍から20倍まで幅広い希釈倍率を使い分けます。
シートやフロアマットなどの布製品には10~20倍希釈、樹脂パーツには15~20倍希釈が適しています。
特に汚れがひどい部分のみ、5倍希釈を使用します。
車内は様々な素材が使われているため、部位ごとに適切な濃度を選ぶことが重要です。
革シートには使用できませんが、ファブリックシートには効果的です。
ダッシュボードなどの樹脂部分は、紫外線で劣化していることが多いため、薄めの濃度から始めましょう。
車内清掃の希釈倍率目安:
• フロアマット(取り外し可能):5~10倍
• ファブリックシート:10~15倍
• ドアトリム(布部分):15倍
• 樹脂パーツ:15~20倍
• ガラス内側:20倍
pH値と希釈倍率の関係

pH値は希釈によって段階的に下がり、それに伴って洗浄力も変化します。
原液のpH値が12.5の場合、10倍希釈でpH11.5、100倍希釈でpH10.5程度になります。
この関係を理解することで、目的に応じた最適な希釈倍率を選択できます。
pH値の変化は対数的であるため、希釈倍率とpH値の関係は単純な比例関係ではありません。
例えば、2倍希釈ではpH12.2程度ですが、4倍希釈でもpH11.9程度までしか下がりません。
大幅にpH値を下げたい場合は、高い希釈倍率が必要になります。
希釈倍率とpH値の関係表:
| 希釈倍率 | pH値(原液pH12.5の場合) | 洗浄力 | 適用例 |
|---|---|---|---|
| 原液 | 12.5 | 最強 | 業務用(要注意) |
| 2倍 | 12.2 | 非常に強い | 頑固な油汚れ |
| 5倍 | 11.8 | 強い | キッチン周り |
| 10倍 | 11.5 | 中程度 | 一般的な掃除 |
| 20倍 | 11.2 | やや弱い | デリケート素材 |
| 50倍 | 10.8 | 弱い | 仕上げ拭き |
| 100倍 | 10.5 | 非常に弱い | すすぎ |
色落ちを防ぐという観点では、pH11.5以下での使用が推奨されます。
これは10倍希釈に相当し、多くの場面で安全性と洗浄力のバランスが取れた濃度といえます。
希釈時の注意点と手順
正確な希釈を行うことは、アルカリ電解水を安全に使用する上で最も重要なポイントです。
適当な希釈では、効果が得られないばかりか、素材を傷める原因にもなります。
ここでは、プロも実践している正確な希釈方法を紹介します。
まず、希釈に使用する水は、水道水で問題ありません。
ただし、硬度の高い水を使用すると、アルカリ電解水の効果が低下することがあります。
可能であれば、軟水を使用することで、より高い洗浄効果が期待できます。
正確な希釈の手順:
• 清潔な容器を用意する(目盛り付きが望ましい)
• 必要な希釈倍率を確認する
• 水を先に入れる(泡立ち防止のため)
• アルカリ電解水を少しずつ加える
• よく混ぜて均一にする
• pH試験紙で確認する(可能であれば)
希釈時の注意事項:
• 必ず換気の良い場所で作業する
• 手袋を着用する(原液は特に注意)
• 目に入らないよう注意する
• 金属製の容器は使用しない
• 作った希釈液は早めに使用する
• 余った液は適切に処分する
希釈液は時間の経過とともに中性化が進みます。
特に、高倍率で希釈したものは、効果が早く低下します。
使用する分だけを都度希釈することで、常に最適な洗浄力を保つことができます。
色落ちテストの正しいやり方

アルカリ電解水を使用する前に、必ず色落ちテストを行うことが重要です。
このテストを省略すると、大切な衣類や家具を台無しにしてしまう可能性があります。
ここでは、プロも実践している確実な色落ちテストの方法を解説します。
目立たない箇所でのテスト方法
色落ちテストは、必ず目立たない箇所で行います。
衣類であれば裾の裏側、カーペットであれば家具の下になる部分、革製品であれば底面など、万が一色落ちしても支障のない場所を選びましょう。
この選択が、リスクを最小限に抑える第一歩となります。
テストを行う箇所は、できるだけ本体と同じ条件の場所を選ぶことが大切です。
例えば、ジャケットの場合、表地だけでなく裏地もテストする必要があります。
素材や染色方法が異なる場合があるため、それぞれ個別にテストを行いましょう。
テスト箇所の選び方:
| アイテム | テスト推奨箇所 | 避けるべき箇所 |
|---|---|---|
| 衣類 | 裾の裏側、縫い代部分 | 前身頃、襟元 |
| カーペット | 家具の下、端の部分 | 中央部、目立つ場所 |
| ソファ | 座面の下、背面下部 | 座面、肘掛け |
| カーテン | 裾の折り返し部分 | 日の当たる表面 |
| バッグ | 底面、内側ポケット | 正面、持ち手 |
テスト方法は簡単です。
まず、白い布(綿100%が理想的)に希釈したアルカリ電解水を含ませます。
次に、テスト箇所に軽く押し当て、10秒程度待ちます。
その後、布に色が移っていないか確認します。
色落ちテストの具体的手順:
• 白い綿布を用意する(ティッシュでも可)
• 使用予定の濃度に希釈した液を準備
• 布に少量含ませる(濡らしすぎない)
• テスト箇所に軽く押し当てる
• 10秒待って布を確認
• 色移りがなければ、少し強めにこする
• 再度色移りを確認
テスト時間と確認ポイント

色落ちテストでは、時間管理が重要です。
アルカリ電解水の影響は、接触時間に比例して大きくなるため、実際の使用時間を想定したテストを行う必要があります。
短時間のテストで問題なくても、長時間の使用で色落ちすることがあります。
テスト時間の目安は、実際の使用時間の2倍程度を見込むと安全です。
例えば、しみ抜きで5分程度の処理を予定している場合、テストは10分間行います。
この余裕を持たせることで、予期せぬトラブルを防ぐことができます。
時間別の確認ポイント:
• 即座(10秒以内):激しい色落ちの有無 • 1分後:軽微な色移りの確認 • 5分後:染料の安定性を評価 • 10分後:長時間使用の可否を判断 • 30分後:浸け置き洗いの可否を確認
確認すべきポイントは、色移りだけではありません。
素材の風合いの変化、光沢の喪失、硬化や軟化なども重要な確認事項です。
特に、高級素材や思い入れのある品物の場合は、これらすべての項目を慎重にチェックしましょう。
確認項目チェックリスト:
| 確認項目 | 確認方法 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 色移り | 白布での拭き取り | わずかでも色がつけばNG |
| 変色 | 目視で比較 | 色調の変化があればNG |
| 風合い | 触感で確認 | ゴワつき、柔らかくなりすぎはNG |
| 光沢 | 光の反射を確認 | 艶が失われたらNG |
| 収縮 | サイズを測定 | 1%以上の収縮はNG |
色落ちした場合の対処法
万が一、色落ちが発生してしまった場合でも、適切な対処により被害を最小限に抑えることができます。
重要なのは、慌てずに迅速に行動することです。
色落ちに気づいたら、まず第一に、これ以上の被害を防ぐことを考えましょう。
即座に行うべき応急処置は、大量の水で洗い流すことです。
アルカリ電解水を中和するために、できるだけ早く水で希釈します。
可能であれば、流水で5分以上すすぎ続けることで、アルカリ成分を除去できます。
応急処置の手順:
• すぐに処理を中止する
• 大量の水で洗い流す(5分以上)
• 清潔なタオルで水分を吸い取る
• 自然乾燥させる(熱は加えない)
• 色落ちの程度を確認する
• 必要に応じて専門店に相談する
色落ちの程度によって、その後の対処法が変わります。
軽微な色落ちであれば、市販の色止め剤を使用することで、これ以上の色落ちを防げる場合があります。
しかし、大幅な色落ちの場合は、染め直しが必要になることもあります。
色落ち後の対処法:
| 色落ちの程度 | 対処法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽微(部分的) | 色止め剤使用 | 同系色で目立たなくする |
| 中程度 | 部分染め | プロに相談を推奨 |
| 重度(全体的) | 全体染め直し | 元の色に戻すのは困難 |
| 修復不可能 | 別用途への転用 | 雑巾や掃除用に |
予防が最良の対策であることを忘れないでください。
色落ちテストを確実に行い、適切な濃度で使用することで、ほとんどのトラブルは防ぐことができます。
大切な品物ほど、慎重に扱うことが重要です。
衣類の洗濯・しみ抜きでの安全な使い方

アルカリ電解水を使った洗濯やしみ抜きは、正しい方法で行えば、市販の洗剤以上の効果を発揮します。
ここでは、色落ちを防ぎながら、汚れをしっかり落とす実践的な方法を詳しく解説します。
プロのクリーニング店でも採用されている技術を、家庭でも実践できるようにお伝えします。
洗濯前の準備と確認事項
洗濯を始める前の準備が、仕上がりの良し悪しを決定づけます。
まず、洗濯表示を必ず確認しましょう。
水洗い不可のマークがある衣類には、アルカリ電解水も使用できません。
また、色物と白物は必ず分けて洗うことが基本です。
衣類の素材確認も欠かせません。
綿100%の白いTシャツなら問題ありませんが、シルクのブラウスやウールのセーターは要注意です。
混紡素材の場合は、最もデリケートな素材に合わせて処理方法を決めます。
洗濯前のチェックリスト:
• 洗濯表示の確認(水洗い可否)
• 素材の確認(タグを見る)
• 色落ちテストの実施
• ポケットの中身を確認
• ファスナーやボタンを閉める
• 汚れのひどい部分をマーキング
• 適切な希釈倍率を決定
汚れの種類と程度も事前に把握しておきましょう。
油性の汚れ、たんぱく質系の汚れ、泥汚れなど、それぞれに最適な前処理があります。
アルカリ電解水は油性の汚れに特に効果的ですが、泥汚れには物理的な処理も必要です。
汚れの種類別前処理:
| 汚れの種類 | 前処理方法 | アルカリ電解水の効果 |
|---|---|---|
| 皮脂・汗 | 直接スプレー | 非常に高い |
| 食べこぼし | ブラシで除去後スプレー | 高い |
| 泥汚れ | 乾燥後ブラシで落とす | 中程度 |
| 血液 | 冷水で予洗い | 中程度 |
| インク | 専用処理後に使用 | 低い |
しみ抜きの手順
しみ抜きは、洗濯の中でも特に技術を要する作業です。
アルカリ電解水を使用することで、多くのしみを効果的に除去できますが、正しい手順を踏むことが成功の鍵となります。
ここでは、プロが実践している確実な方法を紹介します。
裏側に布を当てる
しみ抜きの基本は、汚れを他の部分に広げないことです。
そのために、必ずしみの裏側に白い布を当てます。
この布が、溶け出した汚れを吸収し、衣類の他の部分への色移りを防ぎます。
タオルやキッチンペーパーでも代用できます。
布を当てる際のポイントは、十分な厚みを確保することです。
薄い布1枚では、汚れが貫通してしまう可能性があります。
古いタオルを4つ折りにするなど、しっかりとした厚みを作りましょう。
また、処理中に何度か新しい面に変えることも重要です。
裏当て布の選び方:
• 白い綿100%の布が理想的
• 十分な吸水性があること
• 色柄物は避ける(色移りリスク)
• 使い捨てできるものが便利
• 大きめのサイズを用意
叩き洗いのコツ
叩き洗いは、しみ抜きの要となる技術です。
こすってしまうと、汚れが繊維の奥に入り込んだり、生地を傷めたりする原因となります。
正しい叩き方をマスターすることで、効果的にしみを除去できます。
叩き洗いの基本は、垂直に軽く叩くことです。
歯ブラシや綿棒を使用し、しみの外側から内側に向かって叩いていきます。
この時、アルカリ電解水を少量ずつ補充しながら作業を進めます。
一度に大量にかけると、しみが広がる原因となります。
効果的な叩き洗いの手順:
• しみの外周から中心に向かって叩く
• 軽く短いストロークで叩く
• 汚れが浮いてきたら吸い取る
• きれいな部分で再度叩く
• 必要に応じて液を補充
• 裏当て布も適宜交換
叩く強さは、素材によって調整が必要です。
厚手の綿素材なら多少強めでも問題ありませんが、薄手の生地や合成繊維は優しく扱いましょう。
目安として、生地が凹む程度の力加減が適切です。
すすぎ1回で完了
アルカリ電解水の大きなメリットは、すすぎが1回で済むことです。
界面活性剤を含まないため、泡立ちがなく、すすぎ残しの心配がありません。
これにより、水の使用量を大幅に削減でき、時間も節約できます。
すすぎの際は、水温に注意しましょう。
ぬるま湯(30~40℃)を使用すると、アルカリ成分が効率よく除去できます。
ただし、熱すぎる水は色落ちや縮みの原因となるため避けてください。
冷水でも問題ありませんが、すすぎ時間を少し長めにとると良いでしょう。
効率的なすすぎ方法:
| 方法 | 時間 | 水温 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 手洗い | 3~5分 | 30~40℃ | 優しく押し洗い |
| 洗濯機 | 標準コース | 水道水温 | 脱水は短めに |
| シャワー | 2~3分 | ぬるま湯 | 水圧は弱めに |
洗濯機使用時の注意点
アルカリ電解水を洗濯機で使用する場合、いくつかの注意点があります。
まず、洗濯機の材質を確認しましょう。
ステンレス槽なら問題ありませんが、一部の樹脂製部品は長期使用で劣化する可能性があります。
使用量は、通常の洗剤の半分程度で十分です。
泡立たないため、少ないように感じるかもしれませんが、洗浄力は十分に発揮されます。
むしろ、入れすぎると衣類に残留しやすくなるため、適量を守ることが大切です。
洗濯機での使用方法:
• 水量に対して0.1~0.2%の濃度で使用
• 洗濯物は詰め込みすぎない
• 水温は40℃以下に設定
• すすぎは1回でOK
• 柔軟剤は不要(静電気防止効果あり)
• 洗濯後は洗濯槽を乾燥させる
洗濯コースの選択も重要です。
デリケートコースや手洗いコースを選ぶことで、衣類への負担を軽減できます。
特に色物や混紡素材の場合は、穏やかな水流で洗うことをおすすめします。
部分洗いと全体洗いの使い分け
効率的な洗濯のためには、部分洗いと全体洗いを適切に使い分けることが重要です。
すべての衣類を同じように洗うのではなく、汚れの程度や場所に応じて処理方法を変えることで、衣類を長持ちさせることができます。
部分洗いが適している場合は、襟や袖口などの特定の箇所だけが汚れているケースです。
この場合、汚れた部分にのみアルカリ電解水をスプレーし、5分程度置いてから通常の洗濯を行います。
全体を強く洗う必要がないため、生地への負担が軽減されます。
使い分けの基準:
| 洗い方 | 適用ケース | 処理方法 |
|---|---|---|
| 部分洗い | 襟・袖の汚れ、食べこぼし | スポット処理後、通常洗濯 |
| 全体洗い | 汗臭い、全体的に汚れている | 全体に噴霧または浸け置き |
| 併用 | 部分的に頑固な汚れ+全体も汚れ | 部分処理後、全体洗い |
部分洗いのテクニック:
• 汚れ部分を水で湿らせる
• アルカリ電解水を直接スプレー
• 軽くもみ洗いする
• 5~10分放置
• そのまま洗濯機へ
• 他の衣類と一緒に洗濯可能
全体洗いの際は、浸け置き洗いも効果的です。
洗面器やバケツに希釈したアルカリ電解水を作り、衣類を30分程度浸けておきます。
その後、軽くもみ洗いしてから洗濯機で仕上げます。
この方法は、汗臭さが気になる衣類に特に効果的です。
色落ちリスクを最小限にする使用上の注意

アルカリ電解水を安全に使用するためには、細かな使用方法にも注意を払う必要があります。
スプレーの仕方、温度管理、時間管理など、一つ一つの要素が色落ちリスクに影響します。
ここでは、実践的な使用上の注意点を詳しく解説します。
スプレー時の距離と量
スプレーの距離と量は、意外に重要な要素です。
近すぎると一箇所に集中して強い影響を与え、遠すぎると効果が薄れます。
最適な距離は、対象物から20~30cmです。
この距離なら、均等に噴霧でき、部分的な色落ちを防げます。
スプレーの量も、多ければ良いというものではありません。
「湿る程度」が基本です。
びしょびしょに濡らすと、アルカリ成分が必要以上に浸透し、色落ちのリスクが高まります。
また、乾燥に時間がかかり、素材によってはシミの原因にもなります。
適切なスプレー方法:
• 距離:20~30cmを保つ
• 角度:垂直ではなく45度の角度で
• 量:表面が軽く湿る程度
• 動作:一箇所に留まらず動かしながら
• 回数:一度に大量より、少量を複数回
• 範囲:汚れより少し広めにスプレー
スプレーパターンも工夫しましょう。
円を描くように動かすことで、均一な塗布が可能です。
また、縦横に交差させるようにスプレーすることで、ムラを防ぐことができます。
特に大きな面積を処理する場合は、区画を分けて順番に作業すると良いでしょう。
スプレー時の注意事項:
| 項目 | 推奨 | 避けるべき |
|---|---|---|
| 換気 | 窓を開けて作業 | 密閉空間での使用 |
| 保護 | マスク・手袋着用 | 素手での作業 |
| 周囲 | 新聞紙等で養生 | 他の物への飛散 |
| 姿勢 | 風下に立たない | 顔に向けてスプレー |
温度による影響
温度は、アルカリ電解水の効果と色落ちリスクの両方に大きく影響します。
一般的に、温度が高いほど洗浄力は向上しますが、同時に色落ちのリスクも高まります。
最適な使用温度は20~40℃の範囲です。
冷水での使用は、色落ちリスクは低いものの、洗浄力が十分に発揮されません。
特に油汚れは、ある程度の温度がないと落ちにくくなります。
一方、50℃を超える高温では、染料の結合が弱まり、色落ちしやすくなります。
温度別の効果と注意点:
• 10℃以下:効果が大幅に低下、使用非推奨
• 20~30℃:バランスが良い、日常使いに最適
• 30~40℃:洗浄力向上、色物は注意
• 40~50℃:頑固な汚れに効果的、白物のみ推奨
• 50℃以上:色落ちリスク大、使用を避ける
季節による温度管理も重要です。
夏場は水温が高くなりがちなので、必要に応じて冷水を混ぜて調整します。
冬場は逆に、ぬるま湯を使用することで効果を維持できます。
ただし、急激な温度変化は素材にストレスを与えるため避けましょう。
温度管理のコツ:
| 季節 | 課題 | 対策 |
|---|---|---|
| 春 | 温度差が大きい | 室温で保管した水を使用 |
| 夏 | 水温が高い | 冷水で温度調整 |
| 秋 | 朝晩の温度差 | 使用時間帯を選ぶ |
| 冬 | 水温が低い | ぬるま湯で希釈 |
放置時間の管理

放置時間は、アルカリ電解水の効果を左右する重要な要素です。
短すぎると汚れが落ちず、長すぎると色落ちのリスクが高まります。
素材や汚れの種類に応じて、適切な時間を設定することが大切です。
基本的な放置時間は5~10分です。
この時間で、アルカリ電解水が汚れに浸透し、分解作用を発揮します。
ただし、デリケートな素材や濃色の衣類は、3~5分程度に短縮することをおすすめします。
放置時間の目安:
• 白物綿製品:10~15分
• 色物綿製品:5~10分
• 合成繊維:5~8分
• 混紡素材:3~5分
• デリケート素材:3分以内
• 革・シルク:使用不可
放置中の管理も重要です。
直射日光が当たる場所や、高温になる場所は避けましょう。
また、完全に乾燥してしまうと、
汚れが再固着する可能性があるため、適度に湿った状態を保つことが理想的です。
必要に応じて、追加でスプレーすることも効果的です。
放置時間管理のポイント:
• タイマーを使用して正確に計測
• 複数の衣類を処理する場合は順番をメモ
• 乾燥を防ぐため、湿度の高い場所で作業
• 放置中は定期的に状態を確認
• 異常を感じたらすぐに中止
• 子供やペットの手の届かない場所で管理
手袋着用の重要性
アルカリ電解水を扱う際の手袋着用は、単なる推奨事項ではなく必須事項です。
pH11以上のアルカリ性溶液は、皮膚のたんぱく質を徐々に分解し、手荒れや皮膚トラブルの原因となります。
特に、長時間の作業や頻繁な使用では、その影響は無視できません。
適切な手袋の選び方も重要です。
薄手の使い捨て手袋では、長時間の使用に耐えられない場合があります。
ゴム手袋やニトリル手袋など、耐薬品性のある手袋を選びましょう。
また、手袋の内側に綿の手袋を重ねることで、快適性が向上します。
手袋選びのポイント:
| 素材 | 特徴 | 適性 |
|---|---|---|
| 天然ゴム | 柔軟性が高い | ◎(アレルギー注意) |
| ニトリル | 耐薬品性が高い | ◎(推奨) |
| ビニール | 安価だが耐久性低い | △(短時間のみ) |
| ポリエチレン | 薄手で使い捨て | ×(不適) |
手袋着用時の注意点:
• 作業前に手袋の破れをチェック
• 手袋を外す際は表面に触れない
• 使用後は裏返して乾燥させる
• 定期的に新しいものと交換
• 手袋を外した後も手洗いを徹底
• 肌が弱い人は二重に着用
万が一、素手で触れてしまった場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
ぬるぬるした感触がなくなるまで、最低でも30秒以上は流水で洗い続けることが重要です。
その後、弱酸性の化粧水などで中和すると、肌への影響を最小限に抑えられます。
プロが使うアルカリ電解水の選び方

市販されているアルカリ電解水には、様々な種類があります。
成分、pH値、製造方法などの違いによって、効果や安全性も異なります。
ここでは、プロの視点から、用途に応じた最適なアルカリ電解水の選び方を解説します。
成分による安全性の違い
アルカリ電解水の成分は、製品によって微妙に異なります。
主成分は水ですが、電解質として使用される物質の違いが、製品の特性を大きく左右します。
この違いを理解することで、より安全で効果的な製品を選ぶことができます。
塩化ナトリウム配合の影響
多くのアルカリ電解水は、電解質として塩化ナトリウム(食塩)を使用しています。
安価で入手しやすいことが理由ですが、いくつかの欠点もあります。
最大の問題は、金属への腐食性です。
塩分が残留すると、錆の原因となります。
塩化ナトリウム配合製品の特徴:
• 製造コストが低い
• 洗浄力は十分にある
• 金属製品には不向き
• 残留すると白い跡が残ることがある
• 長期保存で効果が低下しやすい
特に注意が必要なのは、塩分濃度です。
0.1%以下なら影響は少ないですが、それ以上になると金属腐食のリスクが高まります。
アルミサッシやステンレス製品を頻繁に掃除する場合は、塩化ナトリウムを含まない製品を選ぶことをおすすめします。
塩化ナトリウム配合製品の使用上の注意:
| 対象 | リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 金属製品 | 腐食・錆 | 使用後は水拭き必須 |
| 電子機器 | 基板腐食 | 使用を避ける |
| 大理石 | 白い跡 | 別製品を使用 |
| 車 | 塗装への影響 | 十分なすすぎ |
炭酸カリウム配合のメリット
炭酸カリウムを電解質として使用したアルカリ電解水は、プロの間で高い評価を得ています。
食品添加物としても使用される安全な物質で、金属への腐食性が極めて低いことが特徴です。
価格は高めですが、その分メリットも多くあります。
炭酸カリウムの最大の利点は、残留しても害がないことです。
白い跡も残りにくく、すすぎが不十分でも問題が起きにくいのです。
また、洗浄力も塩化ナトリウム製品と同等以上で、特に油汚れへの効果が高いとされています。
炭酸カリウム配合製品のメリット:
• 金属腐食性が極めて低い
• 残留しても安全性が高い
• 白い跡が残りにくい
• 保存安定性が良い
• 環境への負荷が少ない
• 肌への刺激が比較的マイルド
デメリットとしては、価格が高いことが挙げられます。
塩化ナトリウム製品の2~3倍の価格になることもあります。
しかし、安全性と使い勝手を考えると、長期的にはコストパフォーマンスが良いと言えるでしょう。
pH値別の用途と効果
pH値は、アルカリ電解水を選ぶ上で最も重要な指標の一つです。
用途に応じて適切なpH値の製品を選ぶことで、効果を最大化しながら、素材への影響を最小限に抑えることができます。
ここでは、pH値別の特徴と適した用途を詳しく解説します。
pH11.0~11.5の製品は、日常的な掃除に最適です。
十分な洗浄力がありながら、素材への影響が少ないバランスの良い範囲です。
キッチンの軽い油汚れ、テーブルの拭き掃除、床掃除など、幅広い用途に使用できます。
pH値別の特徴と用途:
| pH値 | 洗浄力 | 安全性 | 適した用途 | 不適な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 11.0~11.5 | 中 | 高 | 日常掃除、デリケート素材 | 頑固な油汚れ |
| 11.5~12.0 | 中~高 | 中 | 一般的な掃除全般 | シルク、革製品 |
| 12.0~12.5 | 高 | 低 | 換気扇、コンロ | 色物衣類 |
| 12.5以上 | 最高 | 要注意 | 業務用、特殊清掃 | 家庭での日常使い |
pH12.0以上の製品は、強力な洗浄力を持つ反面、取り扱いには十分な注意が必要です。
換気扇の頑固な油汚れや、業務用厨房の清掃には効果的ですが、素手で触れることは避け、必ず保護具を着用してください。
選び方のポイント:
• 日常使いならpH11.5前後を選ぶ
• 用途別に複数のpH値を使い分ける
• 初心者は低めのpH値から始める
• 業務用は資格や知識が必要な場合も
• 製品ラベルの用途を必ず確認
保管方法と使用期限
アルカリ電解水は、適切に保管すれば長期間使用できますが、保管方法を誤ると効果が低下します。
特に、pH値の高い製品ほど、保管環境の影響を受けやすいため注意が必要です。
正しい保管方法を知ることで、製品の効果を最後まで活用できます。
最も重要なのは、直射日光を避けることです。
紫外線は、アルカリ電解水を中性化させる作用があります。
暗所保管が理想的ですが、それが難しい場合は、不透明な容器に移し替えるか、箱に入れて保管しましょう。
適切な保管条件:
• 温度:5~25℃(室温保管可)
• 湿度:特に制限なし
• 光:直射日光を避ける
• 容器:密閉できるもの
• 場所:子供の手の届かない場所
• 他製品:酸性洗剤と離して保管
使用期限は、製品によって異なりますが、一般的に製造から1~2年です。
開封後は、なるべく6ヶ月以内に使い切ることをおすすめします。
時間の経過とともにpH値が低下し、洗浄力が弱まるためです。
使用期限の目安:
| 状態 | pH11.5以下 | pH12.0以上 |
|---|---|---|
| 未開封 | 2年 | 1年 |
| 開封後 | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
| 希釈後 | 1週間 | 当日中 |
保管時のNG行為:
• 他の容器への移し替え(劣化の原因)
• 高温場所での保管(車内など)
• 凍結させる(成分が分離)
• 他の洗剤との混合(危険)
• キャップの締め忘れ(炭酸ガス吸収)
効果の確認方法として、pH試験紙を使用することをおすすめします。
定期的にpH値を測定し、明らかに低下している場合は、使用を控えるか、使用量を増やすなどの対応が必要です。
お掃除に万能なアルカリ電解水マイヘルパーION MAXのご紹介
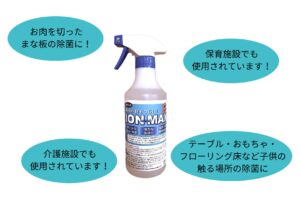
アルカリ電解水は、お掃除に万能な洗浄剤として注目されています。
中でも、マイヘルパーION MAXは、高品質なアルカリ電解水として人気の商品です。
マイヘルパーION MAXは、pH12.5の強力なアルカリ性を持つ「水」です。
苛性ソーダなどの危険性のあるアルカリではなく、電子イオンをたくさん持った特殊なイオン水のため、科学火傷や皮膚刺激はありません。
また、「水」であるため、小さなお子様やペットのいるところでも安心して使用できます。
マイヘルパーION MAXは、強力な洗浄力を持っています。
アルカリイオンが汚れと物体の間に素早く浸透・付着し、付着した汚れの周りと物体の表面は、マイナスイオン同士の働きで反発しあって汚れが取れます。
さらに、マイヘルパーION MAXは、除菌・消臭効果も期待できます。
pH12.5の強アルカリ性のため、大腸菌をはじめノロウイルスを不活化する効果があります。
食中毒の原因であるO-157や大腸菌、ノロウイルス、サルモネラ菌なども除菌するので、キッチン周りで使用するにも最適です。
マイヘルパーION MAXは、環境に優しい洗浄剤でもあります。
優れた洗浄力を発揮しながらも、”水”だから環境汚染がゼロ。
自然の力を最大限に発揮した人と環境に優しい商品です。
まとめ
アルカリ電解水は、環境にやさしく、優れた洗浄力を持つ画期的な洗浄剤です。
しかし、その強力な洗浄力ゆえに、使い方を誤ると大切な衣類や家具を傷めてしまう可能性があります。
本記事で解説した内容を実践することで、色落ちのリスクを最小限に抑えながら、アルカリ電解水の効果を最大限に活用できます。
最も重要なポイントは、素材を正しく見分け、適切な濃度で使用することです。
シルクやウール、革製品などのデリケートな素材には使用を避け、綿や合成繊維でも必ず色落ちテストを実施しましょう。
希釈倍率は用途に応じて調整し、一般的な掃除には10倍希釈を基準とすることをおすすめします。
また、使用時の細かな配慮も色落ち防止には欠かせません。
スプレーは20~30cmの距離から、表面が軽く湿る程度に噴霧し、放置時間は5~10分を目安にしてください。
温度は20~40℃の範囲で使用し、必ず手袋を着用して作業することで、安全性を確保できます。
製品選びにおいては、用途に応じたpH値と成分を確認することが大切です。
日常使いにはpH11.5前後の製品を、金属製品が多い場所では炭酸カリウム配合の製品を選ぶと良いでしょう。
そして、適切な保管により、製品の効果を長期間維持することができます。
アルカリ電解水は、正しく使えば家事の強い味方となります。
本記事の内容を参考に、安全で効果的な使い方を実践していただければ幸いです。
大切な物を守りながら、清潔で快適な生活環境を実現しましょう。